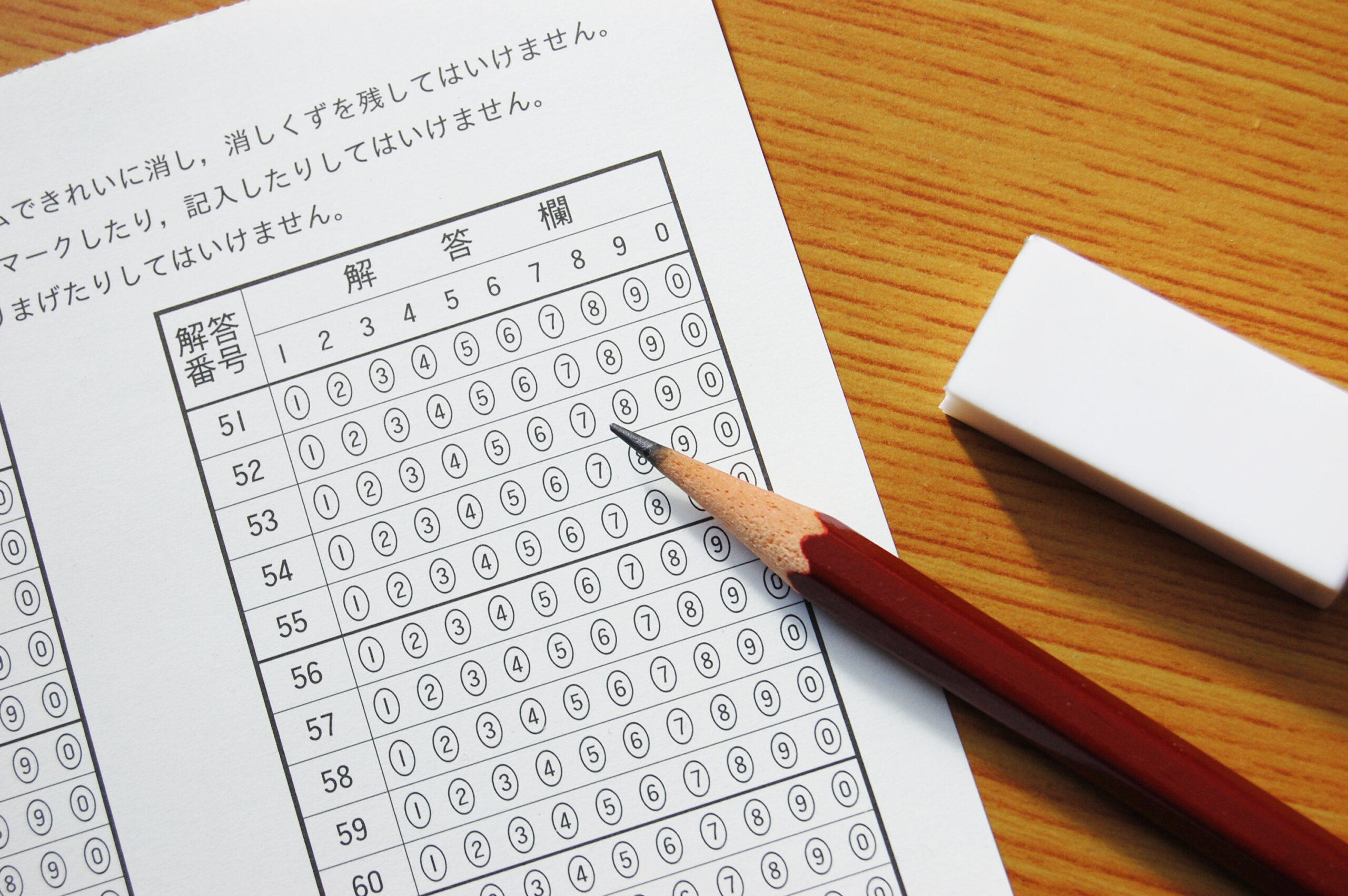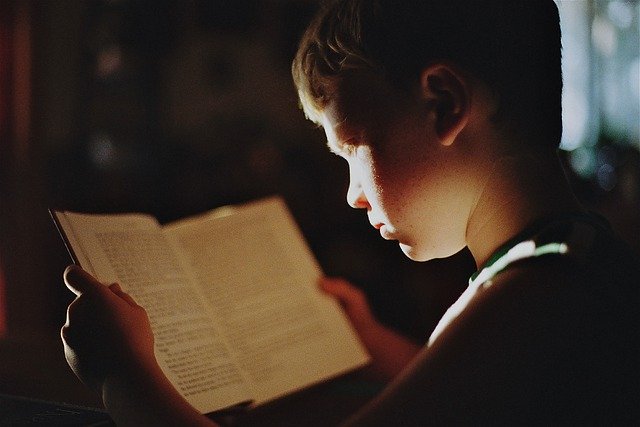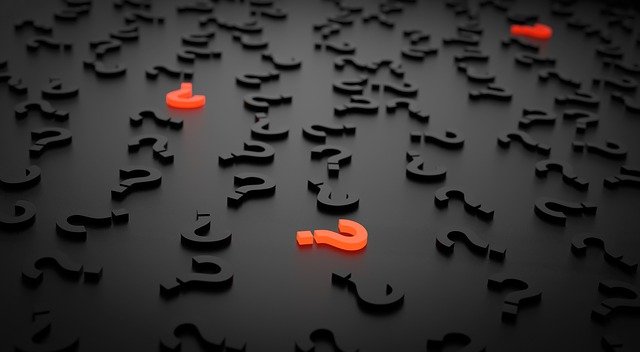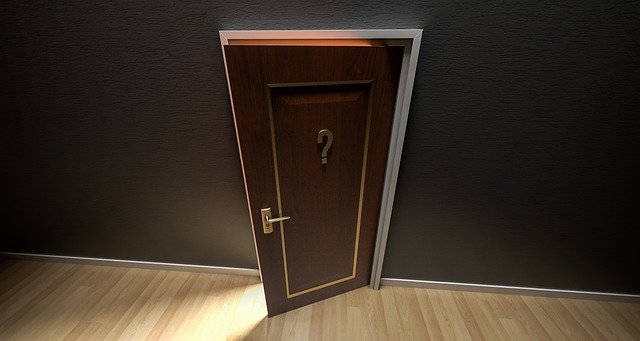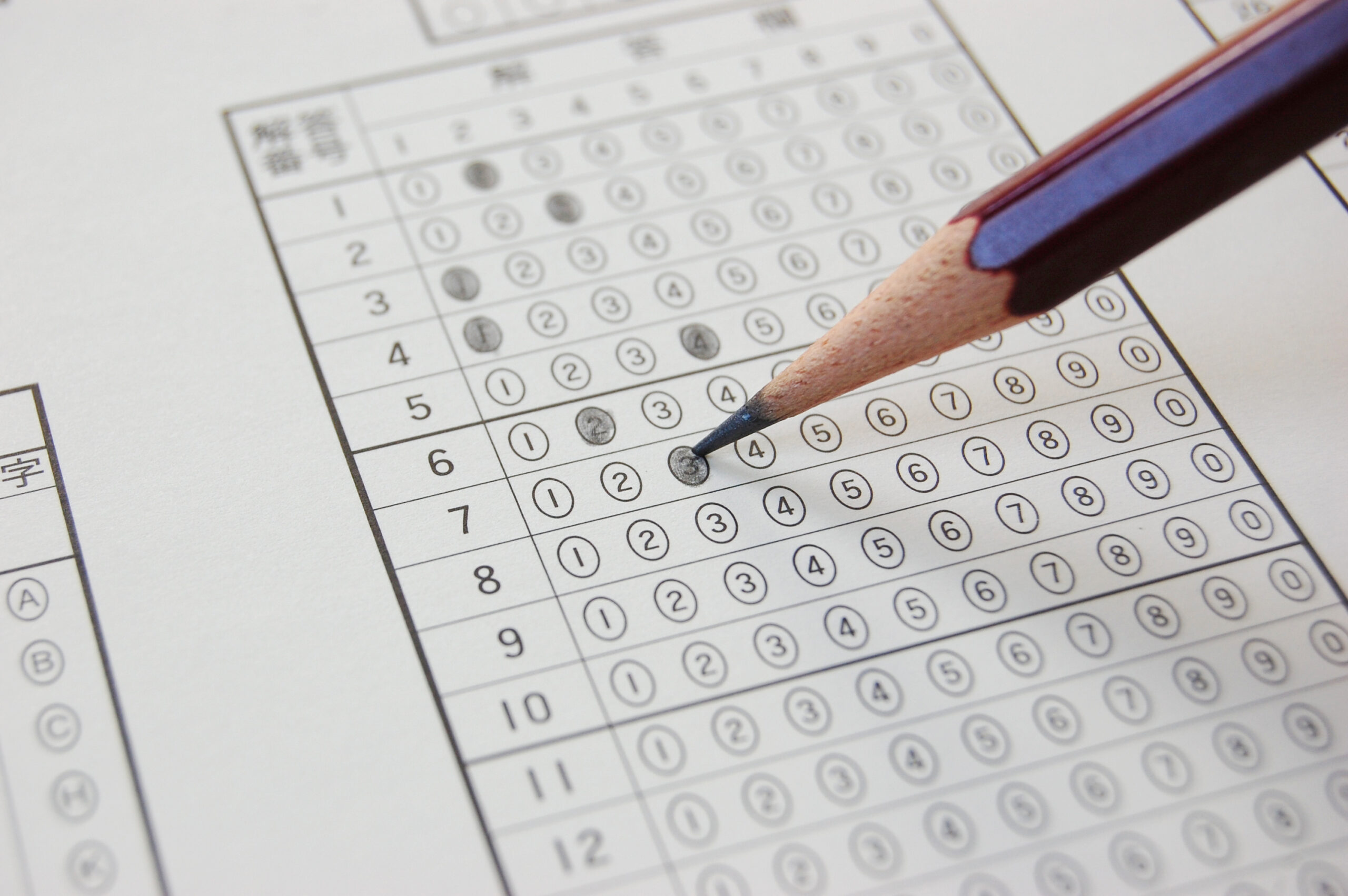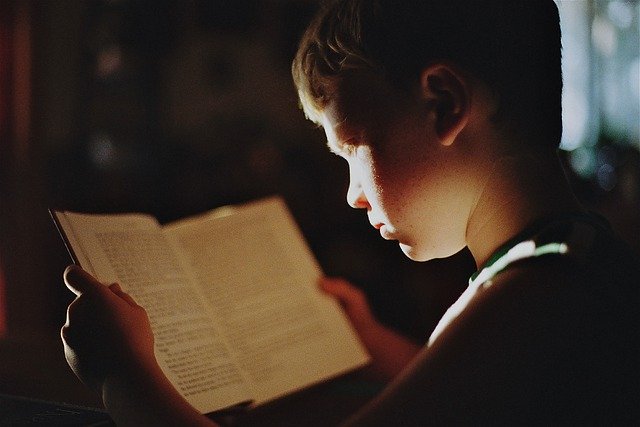
今からごくごく当たり前のことを書こうと思う。
「継続すること」についてである。
さて、果たしてどれだけの人がこれを実行できているだろうか?
身近にはあまりいないとしても、世の中を見渡せば「継続する」という当たり前のことを当たり前に実行している人はたくさん存在するにちがいない。
同時に「継続することで成功をつかんでいる人」も少なくないのではと思える。そうすると「成功する」為には、「継続することが前提」という理論が成り立つ。
さて、ここで私の失敗談をいくつか。
学生時代、中間期末テストがある時は、いつも一夜漬け。たいした結果がでなかったのがほとんど。
受験の際も、コツコツ勉強した感じはなく、途中経過はいい感じであったにもかかわらず、最後には友人に追い抜かされる結果となった。
大学の卒業論文も同様であり、提出期限前日から朝にかけて仕上げるなど、寸前に一極集中することが常。
その後も、体力づくりの為にジムに通うも3ヶ月で終わり、自宅での体幹トレーニングも当然続かず。
ヨガもピアノも9ヶ月程度は続いたが、それ以上はなかった。
ライターになるべく、教室にも通ったことがあったが、結局それも続いていない。
ある採用試験にも、いいところまでいくのだが、毎日コンスタントに勉強することができず、チャンスを逃してしまったこともある。
ここまで過去の失敗談を綴ってきたわけだが、それではなぜ私がこれほどまでに「継続すること」を力説するのか?
それは、最近になりその言葉の意味がよく分かってきたからだ。
つまり「継続すること」で、結果が出始めたということ。
私は、昨年ある国家資格に1発合格することができた。
今までの自分なら試験のちょっと前に勉強し、案の定、結果がダメで「ほら、やっぱりダメだった」で終わっていたと思う。
「また来年に向けてボチボチ勉強をすればいいや」などと。
しかし、なぜか今回は違った。「このまま失敗続きの人生なんて、何かしゃくに障る。人生において何か形に残したい」そんなことを思いつつ、色んな人の姿や言葉を思い出していた。
・あるライタースクールの先生は「シナリオや小説を完成させるには、毎日1時間机に向かうことができるかできないかだ」
→これについては、シナリオや小説は、話の内容よりもまず最後まで完成させることが”至難の業”であることを補足しておきたい。
・昔、ある採用試験にともに挑戦した友人がいたのだが、その友人は見事に合格を勝ち取り私は落ちた。私から合格するための助言を求めたところ「仕事でしんどくても、毎日1時間机に向かえるがどうか」とのことであった。
・移動中の電車で、ドア付近に立っていた男性の老人が「英語の単語帳」を見ていた。
・今も尚、現役で活躍しているサッカーのキングカズさんも、あの年齢で体力をキープできているのは、毎日のトレーニングを欠かさないからなのだろう。
・もう引退されたが、元メジャーリーガーのイチローさんも、あれだけの功績を残せたのはトレーニングを1日も欠かさずに取り組めたことが大きく影響しているはず。
・他にも、ノーベル賞を受賞した研究者の方々も。日々のトライアンドエラーの繰り返しで成功を見いだしているのは周知の事実である。
「そうだ、やっぱり成功を勝ち取るには、日々の目の前の時間に集中し、努力するしかない」そう思えたわけである。
そして私は、まず専門学校の学費を何とか工面すべく、2年間毎月数万円ずつ貯蓄することにした。
いきなり多額のお金を準備することはできないが、少額でも時間をかければ何とかなる。これも「継続すること」の結果である。
そしてお金が貯まったら、次に専門学校に入学。そこからさらに仕事と並行して約2年間勉強。
試験に向け、徐々に緊張が高ぶってくる中、何とか試験には1発合格し、国家資格取得を勝ち取ったわけである。
それまでに計4年を費やした。
振り返ったのだが、今回の国家試験はあまりに膨大な範囲であり、絶対に数ヶ月間の勉強では合格は勝ち取れなかったと思っている。
毎日の少しの時間の積み重ねがあったからこそだったと。
仕事や家事が忙しい人だって、例えば通勤時間の電車の中、昼休憩ご飯を食べた後に参考書を開く。
歩いている時、料理を作っている時、洗濯物をたたんでいる時、見たり書いたりはできなくても、音声だけの講義を聞くことはできる。
私は、以前「まとまった時間がとれないから勉強できない」と自分に言い訳していることがあった。しかし、小間切れの勉強でも成果はあることに気づいた。
「どうせまだまだ先のことだし、モチベーションはなかなかあがらない」とか、「そんな頑張ったって落ちる時は落ちるんだから意味がない。落ちたらそんな努力は無駄になるだろう」
とか、もちろんそんな声も聞こえてきそうなのだが、成功とは結果を出すとは「積み重ねてきた努力したその先にあるもの」である。
もしかすると、運が良い人は「ただ単に運が良い」ではなくて、「努力した人だからこそ運を引き寄せた」の感覚と似ているのかもしれない。
つまり「それを実行した人だけがその権利を得る」ことだと、そう私は思っている。
もう一度言う。
当たり前のことを当たり前に言う。
どんなことにしたって、やはり一朝一夕には成功などあり得ない。1日1日の努力の積み重ねが成功へとつながるのだ。
一度でも継続して成功をつかむことを経験すると、それがいかに大切であるかを実感することとなる。
努力をして成功することを一度でも味わうまでは確かに大変である。もちろん挫折もあるだろう。
しかし頑張って一度経験してしまえば、途端に思考が変わる。
実は私、今年の夏にある別の国家試験に向けけ、日々邁進している最中。
今回の試験はよりいっそう難易度が高いのだが、やれるべきことはやってみるつもりだ。
今回私が述べてきたことを再度実証すべく、ポジティブシンキングで是非とも成功をつかみたい。